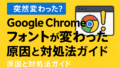「運動会の作文って、何を書けばいいの?」「ただの出来事の説明になってしまう…」と悩んでいませんか?
本記事では、小学生から中学生まで使える運動会の作文の書き方、例文、感動を伝えるテクニック、そして書けない子どもに寄りそう大人のサポート方法までを徹底解説します。
作文が苦手でも大丈夫!自分の気持ちを素直に伝えられるようになります。
運動会の作文ってどう書けばいい?よくある悩み
「何を書けばいいのかわからない」
運動会の作文は、ただ「走った」「応援した」という出来事を並べるだけでは、読んだ人の心に残りにくくなってしまいます。
多くの子どもたちは「何を書いたらいいのかわからない」と悩んでしまいますが、ポイントはそのときの気持ちや考えたことを書くことにあります。
「勝ってうれしかった」「負けて悔しかった」だけで終わらず、「なぜそう感じたのか」「次はどうしたいのか」といった、自分の心の動きを書くと、作文がぐっと良くなります。
「ただの出来事の説明になってしまう」
「運動会がありました。ぼくはリレーに出ました。がんばりました。
たのしかったです。」という作文はよく見かけますが、内容としては少し物足りません。
こうした作文は、事実を並べただけで、読み手がその場面を想像しにくいのが原因です。
「どんな様子だったのか」「どんなことを考えていたのか」をくわしく描写してあげると、同じ出来事でも印象がまったく違ってきます。
「感想がうまく書けない」
感想が書けないときは、「そのときどう感じたか」ではなく「今振り返ってどう思うか」を考えてみるのがコツです。
当日は緊張で覚えていなかったことでも、あとから「やりきれてよかったな」「友だちと協力できたな」と感じることがあります。
過去の気持ち+今の自分の気づきをセットで書くと深みが出ます。
「勝ち負けしか覚えてない…」
運動会というと、赤組・白組の勝敗にばかり目がいきがちです。
でも本当に作文に書くべきなのは、勝ち負けではなく自分の経験と気づきです。
負けても成長できた、仲間と心が通じたなど、そこに注目してみましょう。
先生や親に見せたくなる作文とは?
誰かの心に届く作文とは、自分の言葉で正直に書かれたものです。
うまく書こうとしすぎなくて大丈夫。
短くても、「あ、この子は本当にがんばったんだな」と感じてもらえる文章には力があります。作文は気持ちを伝えるもの。正解はひとつじゃありません。
運動会の作文に入れたい5つの要素
冒頭に季節や天気の描写を入れる
「秋のすずしい風がふく日、ぼくたちの学校では運動会が行われました。」
といったように、季節・天気・空の色・においなどから作文を始めると、情景がすぐに思い浮かびやすくなります。
読む人の心をぐっと引きつける導入になります。
自分の立場・出場競技を明確にする
自分が何に出たのか、どんな気持ちでその競技にのぞんだのかを書くことで、作文にオリジナリティが出ます。
「リレーの最後の走者」「応援団のリーダー」「玉入れでミスをしたけどがんばった」など、自分だけのポジションを明確にしましょう。
緊張・悔しさ・喜びなどの感情を書く
運動会では、たくさんの感情が生まれます。それを正直に書くことが、作文を感動的にします。
「スタート前に手がふるえた」「転んで悔しくて泣いた」「応援の声で力がわいてきた」など、気持ちの描写があると読者の共感を呼びます。
仲間や家族とのやりとりを入れる
友だちに声をかけられた、先生にほめられた、家族が応援してくれたなど、周囲の人との関わりを入れるとストーリーが広がります。
運動会は一人でがんばるだけでなく、たくさんの人とのつながりで成り立っているイベントです。
最後に「気づき」や「来年への思い」をまとめる
作文の締めくくりでは、「来年はもっと早く走れるようにしたい」「今度は応援団に挑戦したい」など、前向きな気づきや目標を書きましょう。
「やりきった」「がんばってよかった」といった言葉も、作文をきれいに締めくくることができます。
【学年別】運動会作文の例文と解説
小学1・2年生向け(100〜150字)
例文
きょうはうんどうかいでした。
おとうさんとおかあさんがみにきてくれて、うれしかったです。
わたしは、たまいれでいっぱいいれられました。がんばったねといわれて、またがんばりたいとおもいました。
解説
この年代はまだ長い文章を書くのがむずかしいので、素直な気持ちを短くまとめることが大切です。
だれと何をしたのか、どう思ったのかが書かれていれば、それでOKです。親や先生は「本人のことば」が出ているかを見守りましょう。
小学3・4年生向け(200〜300字)
例文
ぼくは、うんどうかいのリレーで三ばんめの走者をやりました。
まえの日からドキドキしていて、なかなかねむれませんでした。
でも、スタートラインに立つと、友だちの「がんばれ!」のこえが聞こえて、力がわいてきました。
走っているときは、となりのチームとならんでいて、ぬかされたくないという気持ちで思いきり走りました。
バトンをわたしたあと、先生が「よくやったぞ」と言ってくれてうれしかったです。まけてしまったけど、全力を出せたので、いい思い出になりました。
解説
この学年からは、「緊張・努力・結果・気づき」の流れを意識するだけで、ぐっと完成度が上がります。
自分の気持ちをしっかりと文章にできるようになってきたら、出来事の前後に感情を加えると説得力が増します。
小学5・6年生向け(400字)
例文
秋のさわやかな風がふく中、わたしたちの学校で運動会が行われました。
私は赤組の応援団として、大きな声で声援を送りました。
とくにクラス対抗リレーでは、みんなの気持ちが一つになっているのを感じ、とても感動しました。
私はリレーの四番手として走りました。バトンを受け取る前はとても緊張して、足がふるえるようでしたが、仲間の「いけー!」という声でふっきれて、思いきり走ることができました。
ゴールしたときはぜんそく力を使い切った感じで、達成感がありました。
結果は負けてしまったけど、クラスのみんなと心を合わせてがんばったことが、なによりうれしかったです。
来年も、もっと速く走れるように練習して、またリレーに出たいです。
解説
高学年では、導入→出来事→クライマックス→まとめの構成を意識すると良い作文になります。
また、「一文が長すぎないようにする」「同じ言葉をくり返さない」「気持ちの変化を具体的に書く」など、読みやすさと表現力のバランスも大切になってきます。
中学生向け(600〜800字)
例文(抜粋)
中学最初の運動会。私はクラス対抗の綱引きでリーダーをつとめることになった。
正直、人前で指示を出すのは苦手で、自信もなかった。でも、誰かがやらなければならない役目で、「やってみるよ」と手を挙げた。
初めは声の出し方もうまくいかず、練習でも勝てなかった。
それでも「ここはリズムをそろえよう」「最初は力を抜いて後半で引こう」と工夫しながら作戦を立てた。仲間が協力してくれて、本番では一致団結して初めて勝つことができた。
勝ったことよりも、「一人じゃない」と感じられたことがうれしかった。
失敗しても仲間がいて、自分を信じて動いてくれた。あの日感じた「一体感」は、今でも心に残っている。
解説
中学生は、経験を通じた成長や気づきを丁寧に描写するのがポイントです。
単に「楽しかった」「悔しかった」ではなく、「なぜ」「どう変わったか」といった、自己理解や人間関係の描写を深めることで、大人にも響く作文になります。
「感動した」と言われる作文に仕上げるテクニック
五感を使って描写してみよう
作文に深みを出すためには、見た目だけでなく、音・におい・肌ざわり・気温・気持ちなど、五感を使った表現を入れるのが効果的です。たとえば、
-
「太陽の光がまぶしくて、目を細めた」
-
「土のにおいがふわっと風にのってきた」
-
「手のひらに汗がにじんでいた」
といったように、体験を自分の感覚で表現すると、読んだ人がその場にいるような気持ちになります。
臨場感がぐっとアップし、「共感」や「感動」につながりやすくなります。
比喩や擬音語で場面をリアルに
「走った」だけでは伝わりにくい場面も、比喩や擬音語を加えることで印象的にすることができます。
たとえば
-
「心臓がドラムのようにドクドク鳴った」
-
「ゴールに向かって風のように走った」
-
「歓声がまるで波のように押し寄せてきた」
このように比喩や擬音を使うと、読者に映像や音が浮かぶような文章になります。
ただし、やりすぎるとくどくなってしまうので、作文の中に1〜2か所入れるくらいがちょうど良いです。
セリフや内心を書くと臨場感アップ
作文に「セリフ」や「心の声」を入れると、物語のような流れが生まれ、読者の気持ちを引きつけます。
例
-
「負けてもいい、今は思いきり走ろう!」と自分に言い聞かせた。
-
「がんばれ!」という友だちの声が、耳に残っている。
-
「やったー!」と自然に声が出た。
こうしたセリフや内心は、その場で何を考えていたかがリアルに伝わるので、心の動きが見える作文に仕上がります。
感情が伝わると、それだけで読み手の印象に残ります。
タイトルで心をつかもう
作文のタイトルを「運動会」や「リレー」などシンプルなものにしてしまうと、内容が印象に残りにくくなります。
タイトルでちょっとした感情やドラマを伝えると、読者の興味をひくことができます。
おすすめのタイトル例
-
「手に汗にぎるリレー勝負」
-
「みんなでつかんだ一勝」
-
「負けても得た宝物」
-
「『がんばれ』が背中を押してくれた」
短くても「おっ」と思わせるタイトルにすれば、作文全体に期待が生まれます。
文章を書き終えてから、内容に合ったタイトルをつけるのも良い方法です。
推敲のときにチェックする5つのポイント
作文が書き終わったら、推敲(すいこう)=書いた文章を見直すことがとても大事です。
以下の5つをチェックしてみましょう。
-
同じ言葉をくり返し使っていないか?
→「がんばった」「うれしかった」が多すぎると印象が薄くなります。 -
文章が長すぎて読みにくくないか?
→一文が50文字を超える場合は、区切れる場所がないか見てみましょう。 -
助詞(は・が・を)の使い方は自然か?
→「私が」「ぼくは」「それを」など、文のつながりを意識。 -
感情が伝わる表現が入っているか?
→「楽しかった」だけでなく、「なぜ楽しかったのか」を書く。 -
読んだ人に伝えたいことが伝わるか?
→最後の一文で気づきや思いをきれいにまとめましょう。
この5つを見直すだけで、ぐんと伝わる作文に近づきます。
書けない子どもに寄りそう大人のサポート方法
質問形式で思い出を引き出す
「さあ書こう!」と言われても、子どもにとっては何を書けばよいかわからないことが多いです。
そんなときは、具体的な質問をして記憶を引き出すのが効果的です。
たとえば
-
「どの競技が一番楽しかった?」
-
「緊張したときって、どんな気持ちだった?」
-
「誰の応援が一番うれしかった?」
といった問いかけをすることで、少しずつエピソードが頭の中に浮かび、自然に作文の材料がそろってきます。
一緒に時系列を整理してみる
「時系列がぐちゃぐちゃで何を言ってるのかわからない」と悩む子もいます。
そんなときは、時系列の整理を一緒にしてあげることがポイントです。
「最初に開会式があって、次に何をしたっけ?」「リレーは午前?午後?」と一緒に順を追って並べると、出来事が整理されて自然と構成ができあがります。
親も自分の思い出を話してヒントに
「お母さん(お父さん)は、小学生のとき何の競技が好きだった?」という話題は、子どもにとって作文のヒントになることがあります。
大人の運動会の思い出話を聞くことで、「自分も同じ気持ちだったかも」と気づくことがあります。
作文=他人に伝えるものなので、こうした「人と気持ちを共有する経験」が、作文を書くうえで大きな助けになります。
書くこと=楽しいと思える工夫
作文を「書かされるもの」と思うと、子どもは手が止まってしまいます。
そこで、好きなペンを使う、絵を描いてから書く、録音して音声から文字起こしするなど、書く前段階を楽しくする工夫も効果的です。
「作文って楽しい」「自分の気持ちを伝えるっておもしろい」そんな気持ちが芽生えれば、ぐんと成長します。
書いた作文を褒めて自信をつける
どんなに短くても、書いたこと自体が素晴らしいことです。
「がんばったね」「自分の気持ちが書けたね」と認めることで、子どもは自信を持ち、次も書いてみようという気持ちになります。
たとえ誤字脱字があっても、「この一文、すごくいいね」とポジティブなフィードバックを最初に伝えることが何より大切です。
まとめ
運動会の作文は、ただ出来事を並べるだけではなく、自分の気持ちや成長の記録としてとても価値のある文章です。
学年に合わせた書き方や、感動を伝えるテクニック、サポート方法を知っていれば、誰でも心に残る作文が書けます。
作文が苦手な子も、書き方のコツや大人の寄りそいで、ぐっと書きやすくなります。
大切なのは、正しい表現よりも、「その子らしさ」が表れていること。
子どもたち一人ひとりの運動会のドラマが、作文という形で未来に残りますように。